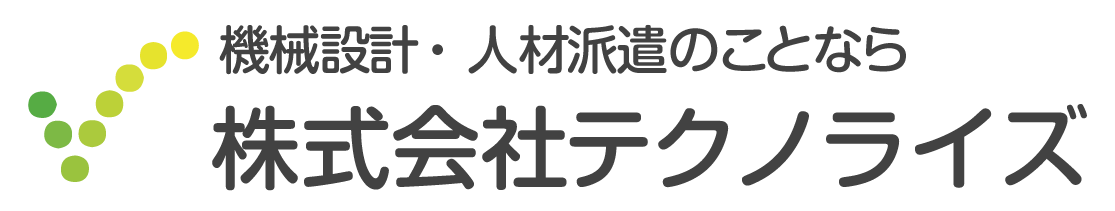3Dプリントをオーダーするなら?必要なものや価格相場など解説
立体的なものを作り出せる3Dプリントは、今や様々な分野で活用されています。
その3Dプリントですが、オーダーして作るのを頼みたい、自分で作るのはハードルが高いからオーダーするときの相場が知りたい…そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は、3Dプリントのオーダーについて
・3Dプリントをオーダーするときに必要なものとは
・3Dプリントをオーダーするときに素材を選ぶポイントとは
・3Dプリントをオーダーするときに知っておきたい相場や価格算出方法とは
・3Dプリントをオーダーするときに注意したい点
などを解説します。
これから3Dプリントサービスにオーダーして制作してもらいたい、と考えていらっしゃる方や3Dプリントをオーダーするときに必要なものなどを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
3Dプリントをオーダーするときに必要なものとは
ここでは、3Dプリントをオーダーするときに必要なものについて解説します。
具体的には以下の通りです。
・3Dデータ
・造形方式についての知識
・素材についての知識
それぞれを詳しく見ていきましょう。
3Dデータ
3Dプリントで制作をオーダーする場合、3Dプリントのデータが必要になります。
3Dプリントのデータとは、物を立体的に作るための設計図のようなものです。
このデータは、コンピュータの中で作られた3Dモデルを、実際に3Dプリンターで印刷するための指示書として使われます。
この3Dプリントのデータには、「.stl」や「.obj」といったさまざまな形式があります。
このデータ形式は、3Dデータを保存するための規格のようなものです。
特にstlファイルはほとんどの3Dプリンターが対応しており、ユーザー間の共有がしやすい標準的なファイル形式となっています。
それではそれぞれのファイル形式を詳しく見ていきましょう。
・OBJファイル(.obj)
OBJファイルは、3Dプリンターに対応しているファイル形式です。
OBJファイルは、同時に別ファイル(MTL形式)を持つため、色やテクスチャー等の表現データを定義することができます。
STLファイルが表現できるのは形状のみなので、3Dモデルに色やテクスチャーの情報が必要な場合はOBJファイルを使用しましょう。
ただ、3Dプリンターで出力する場合、色やテクスチャーを再現できるものはカラープリントに対応した3Dプリンターのみです(専用のインクで、機械が造形しながら着色や模様付けを行います)。
カラープリントができない通常の3Dプリンターでは、色やテクスチャーの印刷はできないため、プリントした後に自分で着色する必要があります。
・STLファイル(.stl)
STLファイルは、3Dプリンターで造形するデータの標準的なファイル形式です。
OBJファイルと違い、色や材料、テクスチャー等の情報を持たないため、形状のみを表現したデータになります。
大半の3DプリンターがSTLファイルを読み込むことができるため、「色やテクスチャーがどうしても必要」などといった特別な事情がなければSTLファイル形式に保存や変換を行えば問題ないでしょう。
造形方式についての知識
3Dプリンターでは様々な素材を使用できますが、造形方式によって、使用できる素材のタイプがそれぞれ異なります。
造形方式は以下のような種類があります。
・熱溶解積層方式(FDM方式)
・光造形方式(SLA方式/DLP方式)
・インクジェット方式(材料噴射方式)
・粉末焼結方式(SLS方式)
・バインダージェッティング方式
熱溶解積層方式(FDM方式)の場合は、熱で溶ける樹脂を細長い紐状にした、フィラメントと呼ばれる素材を使用します。
ほとんどの熱可塑性樹脂がフィラメントとして登場していて、樹脂と異素材を混ぜた合成フィラメントも存在します。
光造形方式(SLA方式/DLP方式)やインクジェット方式(材料噴射方式)の場合は、紫外線で硬化する液体のアクリレート系樹脂を使用します。
粉末焼結方式(SLS方式)やバインダージェッティング方式の場合は、粉末素材を使用します。
樹脂はもちろん、金属粉末や石膏など、粉末状の様々な素材が使用可能です。
素材についての知識
3Dプリントでオーダーする場合、意外と必要なのが3Dプリントで使う素材に関する知識です。
そこまで専門的な知識は必要ありませんが、作成する物や利用の目的によっては、適した素材とそうでない素材があります。
プリントした後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、3Dプリントの素材に関して知っておくといいでしょう。
そして、3Dプリンターの素材と言えばABS樹脂とPLA樹脂が最も一般的でしたが、耐候性の強いASA樹脂、耐熱・耐薬品性の強いPP樹脂、エンジニアリングプラスチックのPC樹脂やナイロン樹脂、そのほか、アクリル樹脂、PETG、熱可塑性ポリウレタン、金属なども3Dプリンターで造形できるようになっています。
3Dプリントをオーダーするときに素材を選ぶポイントとは
ここでは、3Dプリントの素材を選ぶポイントについて解説します。
具体的には以下の通りです。
・仕様
・環境
・機能
・デザイン性
それぞれを詳しく見ていきましょう。
仕様
使用は主に「精度」と「強度」がポイントになります。
造形物の精度には、3Dプリンタ本体の性能や造形方式など、さまざまな要素が影響しますが、素材自体の特性も精度に大きな影響を与えます。
樹脂の種類によっては、加熱時の膨張、冷却時の収縮に加え、加工時に反りや変形が発生する可能性があります。
造形物の強度は、造形方式と素材の強度に依存します。
強度を必要とする場合、強度の高い素材を使いますが、造形物の仕上げに切削や研磨が必要な場合、素材の強度が高すぎると仕上げが難しくなってしまいます。
最終的な造形物に必要な強度と加工性のバランスを考慮し、素材を選定する必要があるでしょう。
環境
素材を選定する上で、造形物の使用環境も重要なポイントです。
例えば、屋外や直射日光のあたる場所で長期間使用する場合は、耐候性の高い素材が必要になります。
耐候性が低いと、変色や強度が低下することがあるためです。
また樹脂の中には高温・低温環境化で物性が大きく変化するものもあります。
製品の使用温度帯によっては、必要な強度を保てず破損してしまうこともあるのです。
他にも、化学物質に触れる可能性がある場合は耐薬品性、湿度の高い環境で使用する場合は吸湿性の低い素材を採用する必要があります。
このように3Dプリンタの素材を選定する際には、使用環境を明確にし、必要な機能を長期間満たせるかどうかを確認することが重要です。
機能
3Dプリンタの造形物には、透明性、柔軟性、難燃性、絶縁性など、さまざまな機能性が求められるものがあります。
機能性を優先する場合は、造形物に必要な機能を明確にした上で、精度や耐久性をどれだけ許容できるかを検討しましょう。
デザイン性
3Dプリンタの造形物には、フィギュアのようにデザイン性が重視されるものもあります。
デザイン性が重視される場合、精度や機能性よりも着色性が選定で重視されるポイントになることもあるでしょう。
着色性においては、
・狙った色で塗装が可能か?
・塗装状態を長期間維持できるか?
などが、オーダー時に素材選定のポイントになります。
3Dプリントをオーダーするときに知っておきたい相場や価格算出方法とは
ここでは、3Dプリントをオーダーするときに知っておきたい相場や価格算出方法について解説します。
3Dプリントをオーダーするときの価格相場は、数千円~数十万円です。
ただし、用途や素材、造形サイズなど複数の要素が価格に影響するため、価格の幅が大きくなります。
3Dプリントをオーダーするときの価格算出方法については、具体的には以下の費用が算出時に関わってきます。
・3Dデータ費用
・3Dプリント費用
・オプション費用
それぞれを詳しく見ていきましょう。
3Dデータ費用
3Dプリント用のデータを持っていない場合は、3Dプリントのオーダー時にデータ制作を依頼できる業者もあります。
価格相場は数万円以上が目安です。
たとえば、3Dプリンターでスマホケースのデータ制作をオーダーする場合の費用は45,000円~になります。
用途やサイズによっては、10万円以上かかるケースもあります。
用途や求めるクオリティによっても価格が異なるため、ホームページや問い合わせで確認しましょう。
3Dプリント費用
3Dデータを元に、実際に3Dプリントを行うのにかかる費用です。
価格相場は数千円から、数十万円以上かかる場合もあります。
前述した通り、用途や材料、造形サイズによって価格は変動するので、それぞれをしっかり確認しましょう。
オプション費用
研磨や塗装などの仕上げ加工や、3D測定などのオプションサービスに対応している業者もいます。
こちらの費用も用途や素材、加工内容によって価格は変わります。
また、製作内容によってはオプション加工が必須となる場合もあるので事前に確認しましょう。
3Dプリントをオーダーするときに注意したい点
ここでは、3Dプリントをオーダーするときに注意したい点を解説します。
具体的には以下の通りです。
・デザインルール
・エラー
・発注先はいくつもある
それぞれを詳しく見ていきましょう。
デザインルール
3Dプリントの業者は、造形中や後処理の最中に発生する破損を未然に防ぐため、それぞれの素材に対するデザインルールを設定しています。
代表的なケースで言うと、
・石膏の場合は2mm以上の厚みが必要
・突起の幅は0.3mm以上
・開ける穴は4mm以上
などです。
作成した3Dデータがデザインルールに適していないと3Dプリントの業者は発注を受け付けてくれません。
3Dデータを自分で作る場合や業者に依頼する際には、利用する予定の3Dプリントサービスが設定しているデザインルールを必ずチェックするようにしましょう。
エラー
3Dプリントの業者にデータを入稿した際、エラーがあって造形できないケースがあります。
特に、3Dデータを自分で作成した場合や3Dプリントの経験が浅い業者が作った3Dデータに多く見られます。
よくあるエラーは以下の通りです。
・面が閉じていない
・デザインルールに適していない
・バッドエッジ
・テクスチャが反映されていない
こうしたエラーが表示された場合はnetfabb cloudなどの無料で簡単に利用できるウェブサービスを利用するか、3Dデータを作成している業者に依頼するなどしてエラーを修正しましょう。
3Dプリントの業者によってはエラーを修正してくれるところもありますので、わからない場合にはエラーの修正をお願いするのも一つの手です。
発注先はいくつもある
3Dプリントの業者を選ぶ理由はそれぞれあるかと思いますが、3Dプリントサービスにも、それぞれ特色があるということを頭にいれておきましょう。
クオリティだけみればA社がよくても、納品スピードはB社、費用はC社がお得…など、選定ポイントはいくつもあります。
3Dプリントをオーダーするときは、自分にとって何が一番重要なのかを考えながらいくつか考えてみるといいでしょう。
まとめ
今回は、3Dプリントサービスにオーダーして制作してもらいたい、と考えていらっしゃる方や3Dプリントをオーダーするときに必要なものなどを知りたい方向けに
・3Dプリントをオーダーするときに必要なものとは
・3Dプリントをオーダーするときに素材を選ぶポイントとは
・3Dプリントをオーダーするときに知っておきたい相場や価格算出方法とは
・3Dプリントをオーダーするときに注意したい点
などを解説しました。
今や様々なものを作り出せる可能性を秘めた3Dプリント技術。
自分で作り出すのが難しくても、オーダーすれば作成できるようになりました。
これから3Dプリントをオーダーして何かを作りたい、と考えていらっしゃる方はぜひ本記事の内容を参考にして、信頼できる業者へオーダーしてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。