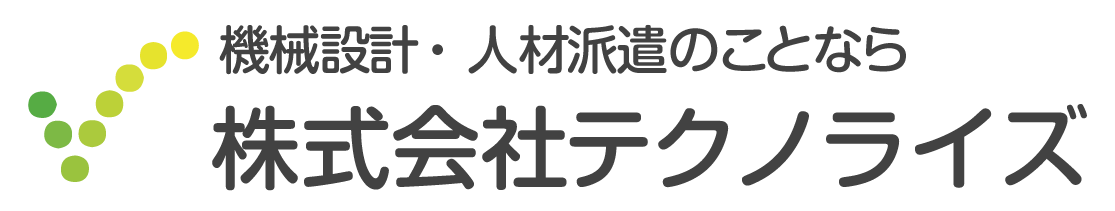3Dプリントで試作がこんなに変わる!時間短縮&高品質
実用化されて以来急速に普及が進み、いまやものづくりに欠かせない存在として重要な加工方法の一つである3Dプリンタ。
その3Dプリントの技術を利用して、製品の試作品などを作りたい、という方も多いのではないでしょうか。
本記事では
・3Dプリントとは
・施策とは
・3Dプリントの技術で施策を行うメリット
・3Dプリントでの施策を外注する際に注意したいポイント
などを解説します。
3Dプリントの技術を利用して、製品の試作品などを作りたい、とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
3Dプリントとは
「3Dプリント」は、「積層造形」とも呼ばれ、デジタルなモデルに基づいて材料を重ねていくことで、物理的な(3D)オブジェクトを作成することを指します。
材料のブロックから削り出して最終製品を作成する切削加工とは異なり、積層造形では材料を付加していくことで最終製品を作り出していくプロセスです。
3Dプリントは、専用のソフトウェアを使用して行います。
個人用から業務用まで幅広い設定に対応しているため、様々な用途に利用することが可能です。
個人的な用途としては、カスタムメイドのアイテムを作成したり、教育用のモデルを作成したり…といった用途に利用されます。
プロフェッショナル向けの用途としては、医療分野ではカスタムメイドの医療用補装具や、自動車・航空宇宙分野のプロトタイプ、軽量構造、建築分野ではモデルやコンポーネントの製造に使用されることが多いです。
試作とは
試作とはメーカーが立案した新製品の開発計画に沿って、各工程で試験的に製品を製造することです。
製造された試作品(プロトタイプ)を用いて、性能、品質、デザイン、コストなどを試験して分析、検証や評価を行います。
たとえば試作品に負荷をかけて耐久性をチェックするなどの各工程で行い、量産化(製品化)を目指していきます。
試作品は原理試作、機能試作、デザイン試作、量産前試作の順に進み、各工程で製造されます。
試作の重要性
製品開発プロセスの各段階にて、性能などの品質に問題がないかチェックするために試作品を製造していきます。
試作開発はアイデアを製品として実現するために重要な役割を持っています。
ここでは試作開発の重要性について、以下のことが挙げられます。
・コスト面での改善や修正
・構造や製造方法の検討
・新技術や製造方法の試験的な運用
それぞれを具体的に見ていきましょう。
コスト面での改善や修正
企画段階で想定していた機能やデザインを実現する場合、予想以上にコストがかかることがあります。
試作品を製作することで、製品化で発生する実際のコストだけでなく不要なコストが発生してる箇所も可視化することが可能です。
選定材料やデザイン変更、設計の修正などコスト面で改善すべきポイントや修正方法が見えるため、試作は量産化に欠かせません。
構造や製造方法の検討
試作品の製作を通じて、品質を確保しつつ、より効率的かつコスト面で有効な構造や製造方法が検討できるようになります。
また、異なる構造や製造方法で製作した試作品の分析や検証を通じ、量産化にもっとも適した構造や製造方法を把握することも可能です。
新技術や製造方法の試験的な運用
試作品の製作段階では、従来の技術や製造方法を用いるだけでなく、新技術や試したことのない製造方法を試験的に取り入れることも可能です。
また、製品化を通じて自社の新技術開発に結び付き、生産技術の向上につながることも期待できます。
試作に用いられる方法
試作品は製品開発プロセスに沿って多く製造されます。
量産は金型を使って効率良く作られることがほとんどですが、少量の試作には金型はコストがかかってしまい不向きです。
そこで、試作では金型以外のさまざまな手法が用いられています。
試作の製作に用いられる主な4つの方法は以下の通りです。
・手作業
・簡易型
・機械加工
・3Dプリント
それぞれを詳しく見ていきましょう。
手作業
素材を切り出す、組み立てる、かんたんな加工をほどこすなどの手作業による試作品製作です。
機器の準備などがなくコストが低く、手軽に実施することが可能です。
ただし、試作品の出来栄えやスピードは、作業者のスキルや技術に左右されます。
簡易型
量産時に使用する金型(本型)と同じ原理の簡易的な金型を製作し、試作を制作する方法です。
本型が金属製であるのに対して、簡易型はシリコンゴムなどを使用します。
マスターモデルがあればかんたんに型が作れ、量産試作などある程度試作品の数が必要なときにも有効です。
本型よりも金型の耐久性は落ちるため連続使用はできませんが、コストを抑えて試作品を製作できます。
機械加工
「切削加工」「塑性(そせい)加工」「射出成形」といった機械加工によって試作品を製作する方法です。
量産品に近い状態での試作が可能なため、最終確認の段階で用いられることが多いです
3Dプリント
近年、3Dプリントの技術が試作制作に用いられるケースが多くなりました。
CADデータを作成して3Dプリンタに読み込ませ、立体造形として試作品を出力する方法です。
データがあればすぐに造形できる手軽さやスピーディさが魅力と言えるでしょう。
3Dプリントの技術で施策を行うメリット
ここでは、3Dプリントの技術で施策を行うメリットについて解説します。
具体的には以下の通りです。
・デザインの自由度が高い
・幅広い素材に対応できる
・施策時間を短縮できる
・コストを抑えられる
・修正が容易
それぞれを詳しく見ていきましょう。
デザインの自由度が高い
3Dプリントの技術を用いて試作を行うメリットの1つとして、デザインの自由度が高い点が挙げられます。
これまでの製造方法は金型や工具が必要なため、複雑な形や細かい部分の再現が難しいケースもありました。
しかし、3Dプリンターは素材を積み上げて形を作るため、曲がった部分や空洞、細かい構造など自由に作ることができます。
幅広い素材に対応できる
3Dプリンターは他の試作製作方法と比較すると、幅広い材料に対応できるメリットがあります。
3Dプリンターに対応した材料は金属、非鉄金属、プラスチック、石膏、ゴムなどがあり、透明な樹脂を使用すれば検証もしやすいでしょう。
同じ設計で材料を変更して、耐久性や熱耐性などの検証をしたいときにも3Dプリントの技術を利用することは向いていると言えます。
施策時間を短縮できる
試作時間を短縮できるのもメリットの1つです。
従来の試作では、図面を作成し製品のパーツを手作業や外注で製作し組み立てる工程が必要なため、時間がかかりやすいことが課題でした。
また、外注の場合は部品の製作や輸送にも時間がかかってしまいます。
しかし、3Dプリントの技術を駆使すれば、治具などの補助パーツも自社ですぐに作ることが可能です。
そのため、試作にかかる時間を短縮し、素早く製品の改善や調整が行えるようになるでしょう。
コストを抑えられる
3Dプリントの技術を利用すれば、材料費だけで試作品を製作できます。
他の製作方法は外注先の選定から依頼、材料の調達までと総合的に発生するコストが大きくなる場合が多いです。
また、自社に3Dプリンタ―が無くても、造形サービス(3Dプリントサービス)を利用して試作品の製作を依頼することも可能です。
修正が容易
3Dプリントの技術を利用すれば手軽に何度も試作品の造形が可能です。
従来の試作方法では、金型の作成や製造工程にコストと時間がかかるため、試作品の修正や再度作り直すことはできませんでした。
しかし、3Dプリンターは修正後のデータを元にすぐに新しい試作品を造形できるため、アイデアの変更や設計の改善を素早く反映することが可能です。
再造形のコストが低いため何度も繰り返して試作が可能になり、最終的に製品を作る際の品質を大きく向上できるでしょう。
3Dプリントでの試作を外注する際に注意したいポイント
ここでは、3Dプリントでの試作を外注する際に注意したいポイントについて解説します。
具体的には以下の通りです。
・対応素材
・寸法精度
・納期のスピード
・3Dプリンターに対するファイル形式
・オプションサービス
それぞれを詳しく見ていきましょう。
対応素材</H3>
3Dプリントサービスを提供している業者を選ぶポイントとして、用途に合わせた素材に対応しているかどうかを確認することが挙げられます。
3Dプリンタにおける素材とは、一般的な2Dのプリンタでいうインクのような存在です。
3Dプリンタは素材を固めることで立体的に製作します。
業者によって対応できる素材は違います。
3Dプリンタの素材は以下のようなものがあります。
・ASA樹脂
・PLA樹脂
・ナイロン樹脂
・石こう
・PP
素材によってメリットデメリットがあり、対応できる素材が多いほど幅広い種類のものを作成することが可能です。
寸法精度</H3>
3Dプリントサービスを提供している業者を選ぶポイントとして、目的に応じた寸法精度の高さを選ぶことも大切です。
例えば出力した部品を使って組み合わせの確認を行いたい場合、寸法精度は高い必要があります。
逆に部品のイメージを確認したいなど精密さを求められない場合は、寸法精度はあまり重要ではありません。
寸法精度は主に以下の5つの要素から決まります。
・解像度
・積層ピッチ
・造形物が冷えるときの反り返り
・サポート材の取り残し
・造形後の変形
上記の要素は、主に使用する装置によって違いが生じます。
ホームページなどから、使用している3Dプリンターのスペックを確認しましょう。
納期のスピード</H3>
試作品の作成などを迅速に進めたい場合などは、納期の確認は重要です。
納期は会社や製作物によってさまざまで、翌日に納品できるケースもあれば、1~2週間かかるケースもあります。
特に高精度な造形では時間がかかることが少なくありません。
必要な期限に間に合うかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
3Dプリンタに対するファイル形式</H3>
自社で3Dプリンタのデータを用意する場合、業者が対応しているファイル形式を事前に確認することがポイントです。
3DデータにはSTL方式やOBJ方式など数十種類のデータの種類がありますが、使用する3Dプリンタによって対応しているデータの種類は異なります。
必要な形式に対応しているかどうか、事前に確認しておきましょう。
オプションサービス</H3>
データ作成や仕上げ加工を行ってくれるのかなど、業者によってオプションサービスの豊富さが違います。
具体的には、以下のようなサービスです。
・3Dデータ作成
・仕上げ加工
・3D測定
自分が利用したいオプションサービスに対応している業者を選びましょう。
まとめ
今回は3Dプリントの技術を利用して、製品の試作品などを作りたい、という方向けに
・3Dプリントとは
・施策とは
・3Dプリントの技術で施策を行うメリット
・3Dプリントでの施策を外注する際に注意したいポイント
などを解説しました。
試作品を作る手法としては従来伝わってきた方法がありましたが、3Dプリントの技術を利用することで様々なメリットがあります。
どのような試作品を作るかにもよりますが、3Dプリントの技術を駆使して色々な試作品を作ってみてはいかがでしょうか。
本記事が、3Dプリントの技術を利用して、製品の試作品などを作りたい、という方の参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。