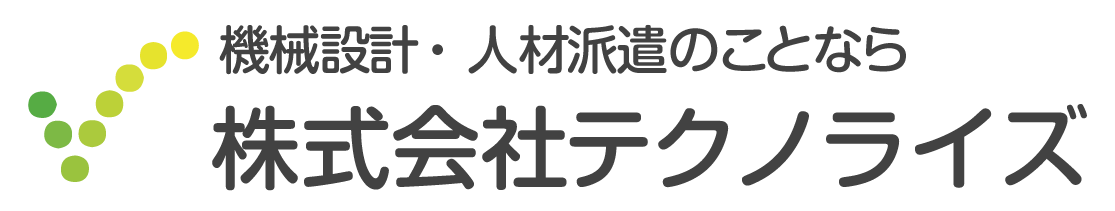3Dプリントで模型を作る!制作に必要なものや活用例など紹介
立体的なものを作り出せる3Dプリントの技術は、今や様々な分野で活用されています。
その3Dプリントですが、自分で3Dプリンタを使って模型を作りたい!…と、お考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は、3Dプリントの模型を作りたい、と考えている方向けに
・3Dプリントで模型を作るときに必要な手順
・3Dプリントで模型を作るときに必要なデーターの作成方法
・3Dプリントで出来る模型以外の活用例
などを解説します。
これから3Dプリントで模型などを作りたい、と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
模型の制作には3Dプリントが便利
3Dプリントとは、3DCADの設計データ(STLデータ)をもとにして、スライスされた2次元の層を1枚ずつ積み重ねていくことによって、立体モデルを製作する技術のことを指します。
薄い層を積み上げる積層方式を基本としながら、液状の樹脂を紫外線で少しずつ硬化させる「光造形方式」や、熱で溶かした樹脂を積み重ねる「FDM方式」など、様々な方式の3Dプリンターが存在します。
近年、3Dデータをもとに立体的なモノを印刷できる「家庭用3Dプリンター」も販売されるようになりました。
模型など小さい造形物の制作には3Dプリントの技術を活用するのが便利です。
3Dプリントで模型を作るときに必要な手順
ここでは、3Dプリントで模型を作るときに必要な手順について解説します。
具体的には以下の通りです。
①必要なものを準備する
②3Dデータを作成する
③スライサーソフトでデータを変換する
④3Dプリンターで模型を出力する
⑤サポート材を取り除く
それぞれを詳しく見ていきましょう。
①必要なものを準備する
3Dプリントで模型を作るときに必要な手順として、まずは必要なものを準備する必要があります。
具体的には以下のものが挙げられます。
・3DCAD
・PC
・3Dプリンター
・サポート材の除去に必要な工具
・3DCAD
アイデアから造形していきたい場合は、モデルを書くための3DCADが必要です。
3DCADには無料版と有料版のソフトがあるため、要望に見合ったものを選んでみてください。
代表的な3DCADには以下のようなものがあります。
<Funsion360>
Autodesk社が提供する3DCADソフトで、オールマイティな機能が搭載されている。
覚える操作は多いが、日本語で操作方法が質問できるコミュニティサイトがあるため学習環境が整っている。
<DesignSpark Mechanical>
コマンドの種類が限られており、初心者でも簡単に3Dデータが作成できる
<BricsCAD>
有料版の3DCADソフトで、機械設計やBIMデータなどの本格的な機能が備わっている
・PC
3DCADソフトが起動できるスペックのPCが必要になりますが、各ソフトの推奨スペックは数ヶ月おきに変わることがあります。
そのため、各3DCADソフトの推奨スペックを調べてから、パソコンを購入することをおすすめします。
・3Dプリンター
3Dデータを出力するための3Dプリンターが必要です。
3Dプリンターには、さまざまな出力方式がありますが、プラモデル作りを楽しみたい方は「光造形方式」を選んでください。
その理由は、光造形方式は液体樹脂を用いるため、表面が滑らかで高精度な仕上がりになるためです。
他の造形方式と比較すると造形時間はかかりますが、高い完成度になるためプラモデル作りに最適です。
・サポート材の除去に必要な工具
3Dプリンターでプラモデルを作る場合は、必要に応じてサポート材を付けます。
造形物が硬化した後に不要なサポート材を除去していく必要があるため、その際に使う工具を用意しておきましょう。
以下のような工具があると、サポート材除去が効率化できます。
・精密ニッパー
・精密ラジオペンチ
・精密マイナスドライバー
・カッターナイフ
・ピンセット
②3Dデータを作成する
模型3Dデータを作成する方法には、以下の3つの方法があります。
1)3DCADで模型を描く方法
2)模型の3Dデータをサイトからダウンロードする方法
3)3Dスキャナーで模型をスキャンする方法
デザインスキルがない方は、3Dデータをサイトからダウンロードする方法がおすすめです。
サイトには、数多くの3Dデータが登録されているので楽しめるでしょう。
また、3Dデータを作成してくれるサービスもありますので、依頼して見るのも一つの手です。
③スライサーソフトでデータを変換する
作成した模型の3Dデータを、スライサーソフトを使用して3Dプリンター用のデータに変換する手順が必要です。
3DCADデータのSTLは代表的なファイル形式ですが、3DプリンターはSTLデータを認識できません。
そのため、スライサーソフトを用いて3Dプリンター用データに変換する必要があります。
このデータを3Dプリンターに読み込ませることで、一層一層を出力していけるようになるのです。
④3Dプリンターで模型を出力する
模型の3Dデータが用意できたら、それを3Dプリンターに読み込ませて印刷していきます。
模型の印刷向きによって、サポート材の量が変わることが多いです。
サポート材を大量に使用すると「コスト増」「後処理が大変」「造形時間が長くなる」なども問題が出てくるため、模型を印刷する向きに拘るといいでしょう。
⑤サポート材を取り除く
模型の印刷を終えたら、サポート材を取り除いていきます。
模型は品質が重視されるため、細部のサポート材を取り除く場合には工具を使用して慎重に取り除いてください。
また、取り除きやすいサポート材を使用すると後処理が簡単になりますので、模型を作る際は考えておくといいでしょう。
3Dプリントで模型を作るときに必要なデータの作成方法
ここでは、3Dプリントで模型を作るときに必要なデータの作成方法について解説します
具体的には以下の通りです。
・3Dスキャナーや3Dプリンターのスキャナ機能でスキャンする
・3DCADソフトを使用してデータをモデリングする
・3DCGツールを使用してデータを作成する
・3Dプリントデータをダウンロードする
・3Dプリントデータ作成サービスを利用する
それぞれを詳しく見ていきましょう。
3Dスキャナーや3Dプリンターのスキャナ機能でスキャンする
3Dデータ化したいモデル本体があるときは、その本体を3Dスキャンすることによってデータを取得する方法があります。
・3Dスキャナーを使う方法
3Dスキャナーは、実際の物体を3Dデータ化するための機器です。
物体の形状を読み取って、そのままコンピュータ上の3Dデータに変換できます。
例えば3Dデータがほしいモデル本体を3Dスキャナで読み込むと、同じ形の3Dデータが作成されます。
このデータを3Dプリンターで出力すれば、元の物体と同じ形のレプリカを作ることも可能です。
3Dスキャナには、物体を回転させながら読み込むタイプや、カメラで撮影するだけで3Dデータ化できるタイプなど、様々な種類があります。
・3Dプリンターを使う方法
3Dプリンターの中には、プリント機能だけでなく、スキャナ機能を持ったプリンターがあります。
3Dプリンター本体に備わったスキャナ機能を利用してデータを取り、そのデータをそのまま3Dプリンターで出力して製品を作る方法です。
3Dスキャナーや、3Dプリンター内のスキャナ機能を用いた方法は、すでにある物の3Dデータを作成するのに便利な方法です。
ただ、すでにある物のデータしか作ることができないため、自分で最始からデータをデザインしたい、作っていきたいという方には不向きでしょう。
3DCADソフトを使用してデータをモデリングする
3DCAD とは、3Dデータを点や線、面や体積を使用して作成するツールのことを指します
ちなみに、CAD(computer aided design)とは、コンピューターで設計やデザインを行うのを支援するツールという意味です。
3DCADは「ワイヤーフレーム」「サーフェス」「ソリッド」の3つの表現方法を用いて、出力するモデルのデータをデザインします。
・ワイヤーフレーム
「点」と「線」を使い、モデルの輪郭を立体的に作成していく方法。
・サーフェス
「点」と「線」を使って「面」を作り、「面」を組み合わせて立体を作成する方法。
紙のような厚みのないペラペラな形状を作成できます。
・ソリッド
「点」と「線」を使って「体積」のある立体を作成する方法。
図のように内部が詰まった立方体を指します。
ちなみに、データ容量は、「ワイヤーフレーム」、「サーフェス」、「ソリッド」の順番で大きくなります。
体積の情報が必要な3Dプリンターのデータには、ソリッドが適しています。
その他の種類で作成したデータは、ソリッドに変換することで3Dプリンター用のデータとして活用可能です。
3DCGツールを使用してデータを作成する
CGツールとは、文字通りCG(computer graphic)を作成するツールを利用して、3Dプリンターのデータを作成する方法です。
CGツールでは「ポリゴンベース」と「スプラインベース」の2種類の方法を使って、データを造形することが可能です。
・ポリゴンベース…四角形や三角形を組み合わせて、プリントするデータを作成する方法
・スプラインベース…曲面を使ってプリント用データを作成する方法
3D用のCGツール(3DCG)は、細かい図形を組み合わせれば、滑らかな曲線を表現できるため、曲線美が重要なフィギュア作成におすすめです。
ただし、正確な寸法を表現しづらいというデメリットがあるため、正確さを要する部品作成には不向きと言えるでしょう。
3Dプリントデータをダウンロードする
3Dプリントに必要な3Dデータは自身で作るだけでなく、オンライン上でダウンロードすることも可能です。
3Dプリントのデータを提供するサイトには、さまざまなジャンルのデータがアップロードされており、必要に応じてダウンロードして使用できます。
配布データには無料のものや有料のものがありますが、どちらもダウンロードしたデータを基にして、3Dプリントのデータの作成練習や作品のアイデア出しに利用できるため、非常に便利です。
ただ、他人が作成したデータのため、著作権や商業利用の可否などのライセンスをしっかりと確認する必要があります。
ダウンロードしたデータを利用する際はきちんとルールを守って、ものづくりに役立てていきましょう。
3Dプリントデータ作成サービスを利用する
オンライン上で希望通りの3Dプリントのデータが見つからず、自身で作るのも難しい場合は、3Dプリントのデータの作成代行サービスなど、プロに任せるのも手段の一つです。
3Dプリントのデータ作成代行サービスにイラストや写真などを提供するだけで、3Dプリントのデータを手に入れることができます。
このように代行サービスを利用すると、3Dプリントのデータ作成にかかる時間や手間を大幅に削減できるのが大きなメリットです。
また、3Dプリントのデータ作成に必要な専門ソフトや高性能なコンピュータも用意する必要がありません。
3Dプリントのデータを作成するスキルやツールが不足している場合は、3Dプリントデータ作成サービスなどプロの手を利用してみると良いでしょう。
3Dプリントで出来る模型以外の活用例
3Dプリンターを活用するとフィギュアやミニチュア、アクセサリー、模型など趣味の小物から実用的な製品までさまざまなものを作り出せます。
例えば、以下のようなものの作成が可能です。
・フィギュア
・ミニチュア
・花瓶
・レジンアクセサリー
・指輪
・小物ケース
・鉄道模型
・カプセルホルダー
・ランプシェード
・名刺スタンド
・口紅
・バックル
・モンキーレンチ
・ロボットアーム
・自動車部品
・金属ギア部品
・建設資材
・美術品
・内臓模型
・等身大の人体模型
上に紹介したように、3Dプリントの技術は様々なものを作ることが可能です。
3Dプリンターの技術は日々進歩しており、新しい材料や印刷方法の開発によって、将来的には現在は作れないものも作れるようになる可能性があるでしょう。
まとめ
今回は、3Dプリントで模型を作りたい、と考えている方向けに
・3Dプリントで模型を作るときに必要な手順
・3Dプリントで模型を作るときに必要なデーターの作成方法
・3Dプリントで出来る模型以外の活用例
などを解説しました。
家庭用3Dプリンタを購入して自分で模型などを制作することも可能ですが、仕上がりが保証されているメリットを考えれば3Dプリントの代行サービスを利用するのも一つの手です。
3Dプリントの代行サービスの価格は、用途や材用、造形サイズによって変動するのでご自身の予算に合わせて利用を考えましょう。
本記事が、3Dプリントで模型を作りたい、と考えている方の参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。